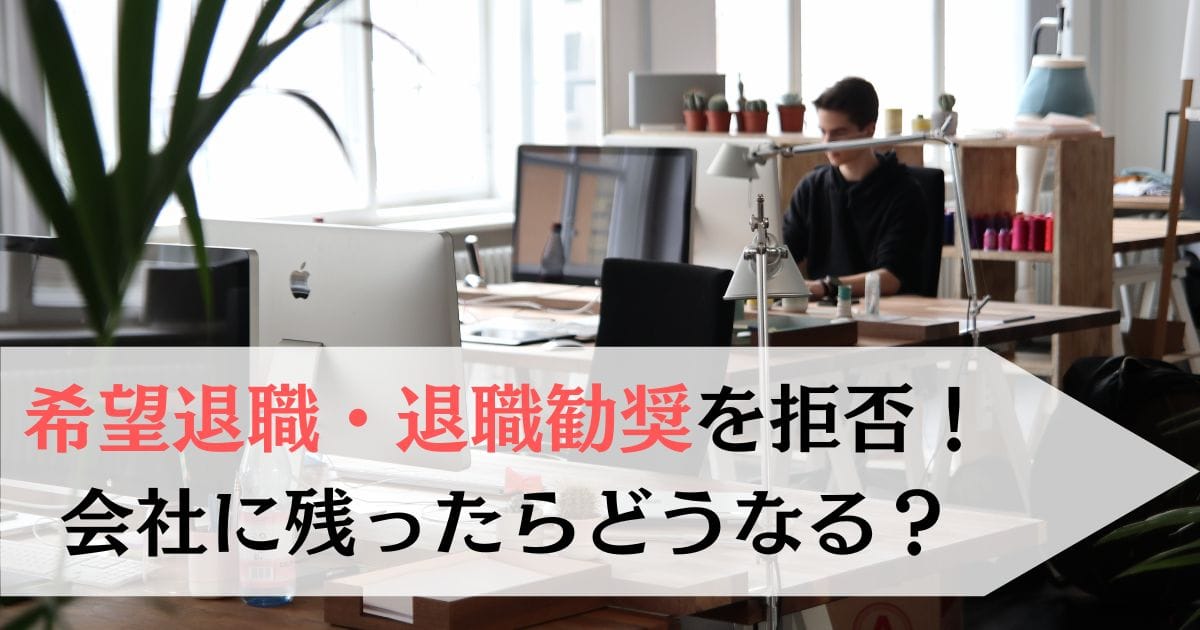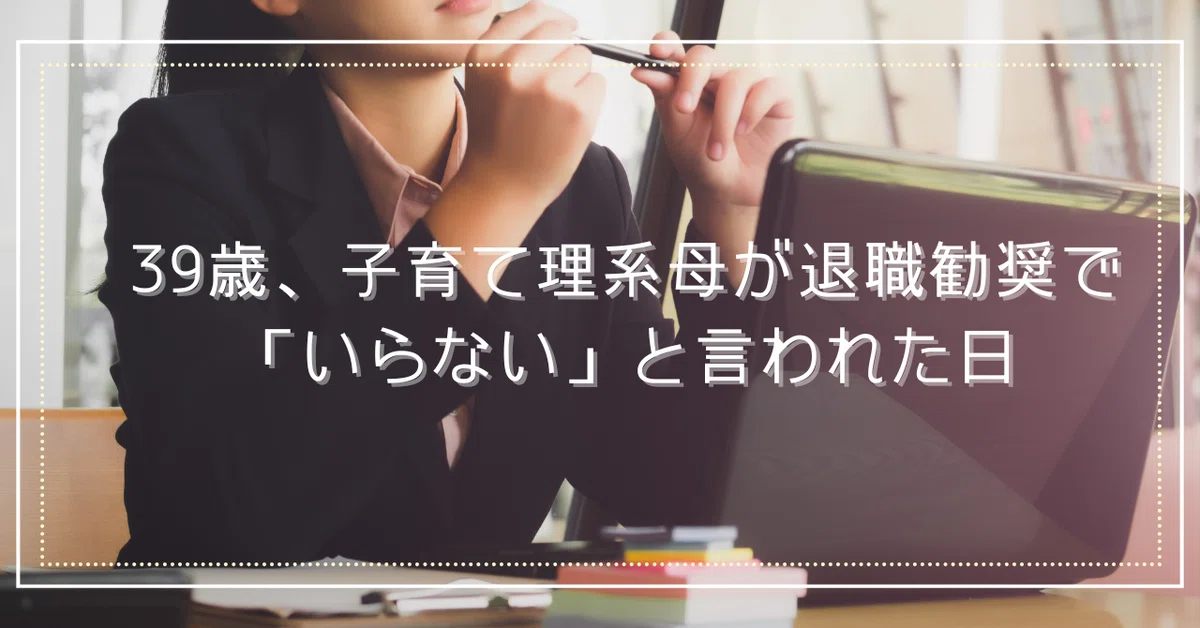希望退職や退職勧奨などの人員整理が実施されると、声がけをされた社員はもちろん、それ以外の社員もいろいろなことを考えてしまいます。
- 退職への声がけを拒否してのいいのか?
- もし拒否したらどうなるのか?
- いつか自分も対象になってしまうのか?
- あの人が辞めたら仕事が回らない
人員削減が実施されると、退職する人はもちろん大変です。
でも会社に残る人も大きな不安や不満、ストレスを抱えながら、その後の会社生活を過ごしていくことになります。
この記事では、「残留を決めた社員」が直面する現実のリスクと、その後の会社生活を乗り切るための具体的な心構えを、企業側の目的と対比させながら解説します。
希望退職・退職勧奨を実施する企業側の目的とは?
企業が希望退職や退職勧奨などで人員整理をすることには、いくつかのメリットとデメリットがあります。
メリット:人員整理が容易になる
- 人員整理を円滑に進めやすい
- 退職勧奨はトラブルを避けてパフォーマンスの低い社員を整理できる
- 希望退職は広く募集できるため、企業イメージを保ちつつスリム化できる
- 退職金の割増で、社員が退職に応じやすくなる
よほどの経営上の危機に陥ってない限り、企業が一方的に従業員を解雇することはできません。
ですが希望退職や退職勧奨などを活用すれば、割増退職金の費用はかかりますが、トラブルを避けて人件費の圧縮と組織のスリム化を達成できます。
デメリット
- 優秀な人材が流出する可能性がある
- 訴訟トラブルのリスク(退職勧奨のしつこい声かけなど)
- 割増退職金などによる一時的なコストの増加
希望退職・退職勧奨は断ることができる
希望退職も退職勧奨も、経営方針の見直しなどにより人員整理をする際に実施される期間限定の退職制度です。
どちらも整理解雇ほどの強制力はないため、退職したくない場合は拒否をして会社に残ることが可能です。
何を言われても、とにかく「辞めません!」を連呼することが大事です。
希望退職・退職勧奨に応じた場合、以下のような優遇措置を受けることができます。
希望退職・退職勧奨の優遇処置
- 退職金の増額
- 有給休暇の買い取り
- 再就職のサポート費用負担
- 会社都合退職になり、失業給付の優遇がある
希望退職・退職勧奨を断ったらどうなる?経営状況で変わる「その後の会社生活」
希望退職・退職勧奨を断った場合どうなるのかは、その時の会社の経営状況や将来性によるところが大きいです。
退職に応じるかどうか考える時は、企業の経営状況がどうなっているか、事業分野の今後の展望を考慮する必要があります。
経営が安定している「黒字企業」の場合(筆者体験談)
筆者が勤めていた企業のように、経営黒字であるのに数年おきに希望退職や退職勧奨を実施するような企業の場合、企業側の目的はダブついた中高年従業員を減らし、組織のスリム化と人件費の削減を定期的に行うことです。
この場合は仮に退職を勧められて断った場合でも、その後の会社生活には大きな影響は無い場合が多いです。
実際に筆者の周りにいた人で退職を断った人が何人かいますが、本人の気持ち以外は特に以前と変わらない会社生活を送っています。
残った場合の懸念点は以下のとおりです。
会社に残った場合の懸念点
- 次回の希望退職・退職勧奨でまた声がけされる可能性が高い
- 次回募集に向けて転職の準備を始めても、次回も同じ条件とは限らない
- 周りの人に退職勧奨の対象だったことがバレて居心地が悪くなる
- 同じような仕事を続ける限り、評価が上がらない
次回募集について
今後また希望退職や退職勧奨が行われるかは現段階では誰にもわかりません。
もし募集があったとしても、退職割増金の減額など優遇条件が変わる可能性はあります。
あまり次回募集について考えても良いことはありません。
気にせず、これまで以上の評価を受けれるように仕事に力を入れた方が良いでしょう。
残留した場合の居心地の悪さについて
自分から「希望退職・退職勧奨を打診された」と言い出さない限り、同僚にバレて気まずい想いをすることはないでしょう。
特に大企業などの従業員が多く、経営が多角化・安定化している企業ならば、他にも退職を断る従業員も多くいるため、周囲の反応を必要以上に気にする必要はありません。
どれかというと、面談相手だった上司や人事との付き合いに悩む場合の方が多いようです。
今後の仕事の評価について
今回希望退職や退職勧奨の打診を受けたということは、例えこれまでの評価が平均的だったとしても貴方は組織にとっていなくても良い存在と言われたようなものです。
これは真面目にこれまでやってきた人にとってはかなりショックなことです。
でもここは前向きに、「これまでの働き方ではダメなんだ」と教えてもらったと思って、より多くのアウトプットを出すような働き方にシフトしていくべきです。
もし今の職場のままでは厳しい場合は、業務内容の変更や他部署への異動も視野に入れていきましょう。
そのままの部署に残って、同じような仕事をしていると、次の希望退職や退職勧奨の時に再度声掛けされるリスクが高まります。
経営が悪化している「赤字企業」の場合
会社の経営が上手くいっていない、事業分野が先細りなものしかない場合、リーマンショックやコロナ禍のような強い経済不安のある時に実施される希望退職・退職勧奨の場合は、そもそも断ることが難しい場合も多いです。
それでも退職を拒んだ場合に起こると予想されることは以下のとおりです。
経営難の企業で残留を決めた場合
- 退職拒否の意思表示後も繰り返し面談が行われる
- 次回の募集があった場合、退職上乗せ金の減額など優遇が減る可能性がある
- 経営がさらに悪化し、拒否権のない整理解雇に移行する場合もある
繰り返し面談が行われる
退職を拒否しても何度も面談が行われる場合がありますが、そもそも執拗に面談を繰り返すこと自体が違法と評価される場合もあります。
また、面談相手から罵倒を受けたり、会社に残ったとしても給与を下げる・配置換えをするなど、精神的な圧をかけられる場合もあります。
その時はやり取りのメモや録音データなどの資料を持って弁護士や労働局に相談しましょう。
👉 希望退職・退職勧奨の面談の録音は必要?
経営が更に悪化し整理解雇の対象になる
希望退職や退職勧奨では従業員が最終的な意思決定をできるのに対し、整理解雇は強制力が強く、従業員の意思は考慮されません。
そのため、整理解雇を実施するには厳しい要件があり、
- 賞与の不支給
- 役員報酬の減額
- 追加の希望退職や退職勧奨の実施
などの施策を行い、それでも経営が厳しいという場合にのみ、整理解雇が認められます。
この状況まで来るとかなり経営的には苦しい状態ですので、通常の退職金はもらえたとしても退職割増金はもらえない可能性が高くなります。
リストラ後の職場環境はどうなる?残された社員の環境
リストラ後、会社の状況は大きく変化します。
特に元から人員が少ない中小企業や、経営不振が続いている企業の場合は職場環境が悪化する可能性があります。
リストラ実施後の職場環境
仕事量が増加
人員削減により仕事量が増える一方で、給料は上昇しないことがあります。
職場環境の悪化によってストレスが増し、会社や経営陣に対する不信感も広がるでしょう。
福利厚生の見直しや削減
リストラを実施しても経営難から更なる人件費削減策を取ること場合があります。
給料やボーナスのカット、福利厚生の見直しや削減、管理職のポスト削減などがその例です。
このような施策が実施されたら、危機感を持った方が良いです。
人員不足の負のループ
リストラによる人員の減少と残った社員のストレスが高まることで、さらなる人員不足が起こる可能性もあります。
特に転職に忌避感が少ない若手社員が辞めていきます。
せっかく育ててきた若手がいなくなり、代わりに新たに人を雇って教育をしなくてはいけません。
また、いなくなった人の分の仕事もこなさなければならず、中堅以上の社員への肉体的・精神的な負担が増します。
業務や生産性に影響が出ることは避けられません。
まとめ:残る決断にも意味がある。大切なのは「自分軸」
希望退職や退職勧奨は、会社の都合であると同時に、社員にとっても大きな人生の分岐点です。
断る・残る──どちらの選択にもメリット・デメリットがあります。
ですが、「断ったら終わり」「残ったら安泰」というわけではありません。
周囲に流されず、自分のキャリアと生活をどうしていきたいのか、自分軸で考えることが何よりも大切です。
リストラは簡単な課題ではありませんが、前向きな姿勢と自己投資によって、社員も会社もより良い方向に進めるはずです。
もし、あなたが今後の働き方に不安を感じているなら、まずは「自分の市場価値を知る」ことが第一歩です。
不安を感じるのは、客観的な情報が少ないからこそ。
- 希望勤務地に求人はどのくらいあるのか?
- 自分の年齢・経歴で年収はどれくらい見込めるのか?
こういった「数字で見える情報」があるだけで、不安が少しずつ解消されていくはずです。
📌 リクナビNEXT:
まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。
自分のペースで探せ、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。
中高年向けの求人も意外と多め。
📌 doda:
求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。
ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。
📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:
本気でキャリアを見直したいなら。
中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。
どのサービスも無料で始められます。
「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。
\5分で簡単登録完了/