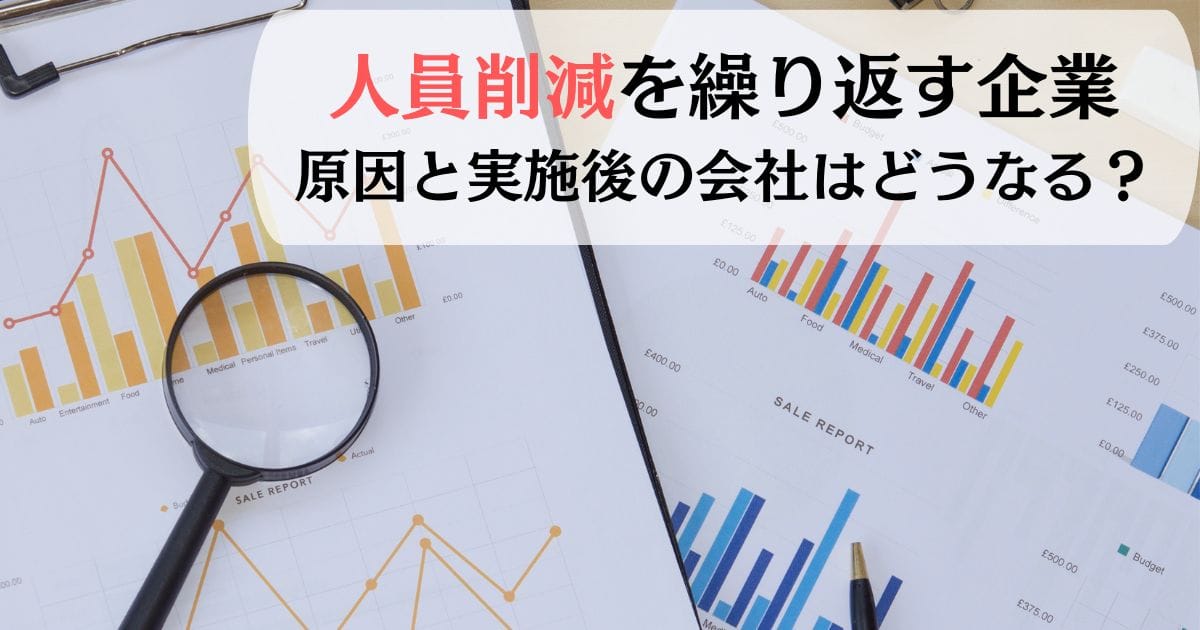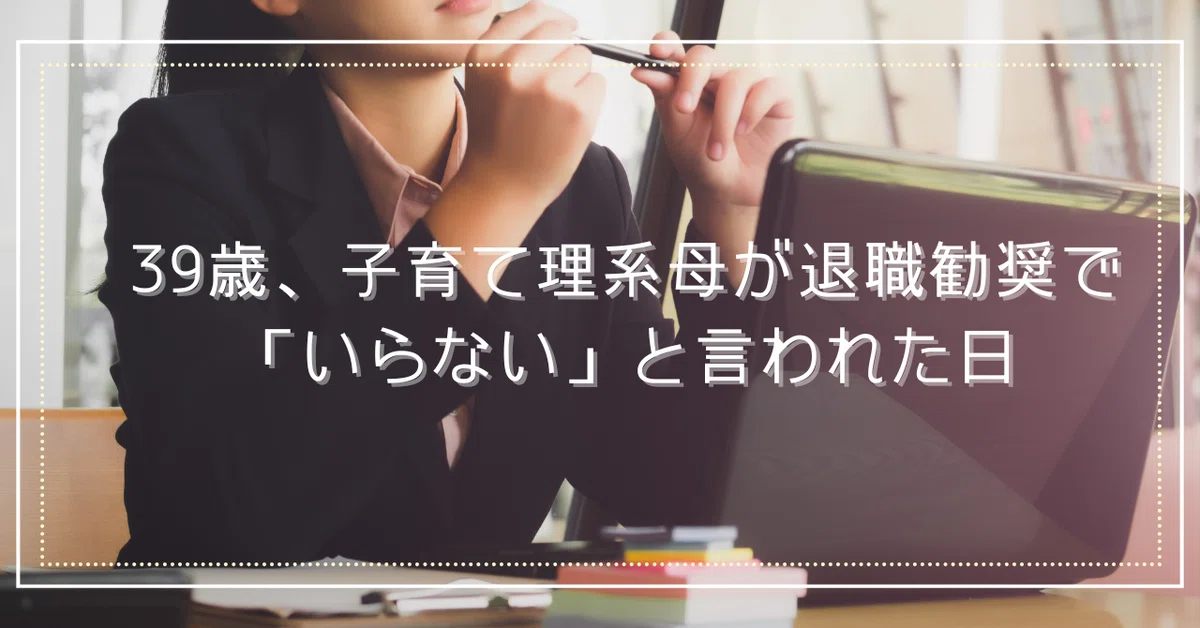近年、大手企業による希望退職のニュースが増えています。
特に数千人規模の人員削減が報道されると、「自分の会社も同じようになるのでは…」と不安になる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、2013年~2024年までの11年間で、国内で複数回の人員削減(希望退職など)を実施した企業と応募人数を一覧にまとめました。
加えて、筆者自身の体験も交えながら、繰り返される人員削減の背景や、社内にどんな影響が出るのかを解説します。
リストラを繰り返す企業:11年間のデータと実態
2013年~2024年にかけて、国内で希望退職者募集や早期退職優遇制度などの人員削減を複数回実施した主な企業をまとめました。
このデータの対象は応募者数を公表した国内企業のみになります。
人員削減策の実施を発表したものの、最終的な応募者数を公表していない企業は含みません。
| 社名 | 業種 | 実施年 | 応募人数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|
| 富士通 | 電気機器 | 2013 2019 2022 | 2,454 2,850 3,031 | 8,355 |
| ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 2013 2014-1回目 2014-2回目 2014-3回目 | 2,316 696 361 1725 | 5,098 |
| 東芝 | 電気機器 | 2016 2019 2021 | 3,449 823 452 | 4,724 |
| JT(日本たばこ産業) | 食料品 | 2015 2022 | 1,754 2,868 | 4,622 |
| パイオニア | 電気機器 | 2013 2019 | 716 950 | 1,666 |
| 大正製薬 | 医薬品 | 2018 2023 | 948 645 | 1,593 |
| ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 2018 2019 | 290 1,266 | 1,556 |
| LIXIL | 金属製品 | 2020 2021 | 497 965 | 1,462 |
| 日立電線 →日立金属に吸収合併 | 2013-1回目 2013-2回目 | 1,112 160 | 1,272 | |
| サニックス | サービス業 | 2015-1回目 2015-2回目 2016 | 609 229 391 | 1,229 |
| スズケン | 卸売業 | 2017-1回目 2017-2回目 2021 | 423 174 511 | 1,108 |
| TSIホールディングス | 繊維製品 | 2015 2021 | 528 351 | 879 |
| ワールド | 繊維製品 | 2015 2020 2021 | 453 294 125 | 872 |
| 三陽商会 | 繊維製品 | 2013 2016 2018 2021 | 270 249 247 180 | 946 |
| エーザイ | 医薬品 | 2014 2019 | 396 300 | 696 |
| 中外製薬 | 医薬品 | 2019 2023 | 172 374 | 546 |
| ワコール | 繊維製品 | 2022 2024-1回目 2024-2回目 | 155 215 | |
| トーアエイヨー | 医薬品 | 2023 2024 | 61 111 | 172 |
| 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 2015 2024 | 634 | |
| 協和キリン | 医薬品 | 2019 2024 | 296 121 | 417 |
| 東北新社 | 情報・通信 | 2024-1回目 2024-2回目 2024-3回目 | 11 124 76 | 211 |
上の表には載せていない、大企業のグループ会社での人員削減
東 芝:東芝テック(2020)と東芝デバイス&ストレージ(2019)で合わせて879人の人員削減
日 立:日立化成、日立マクセル、日立建機で合わせて1,900人の人員削減
富士通:富士通フロンテック(2019)で159人の人員削減
法的側面から見る日本の人員削減
日本の労働法と人員削減
日本の労働法では、人員削減を簡単に進められるわけではありません。
企業はまず労働者との間で労使協議を行い、可能な限り解雇を避けるための方策を講じる必要があります。
- 労使協議の義務
- 解雇予告手当の支払い義務
- 解雇理由の合理性が必要
たとえば、東芝が2023年に行った人員削減では、労働者代表との協議を行い、契約社員の削減やキャリア採用の凍結などを検討したうえで、人員削減数を最小限に抑える努力が見られました。
人員削減とリストラは
日本では「リストラ」という言葉がよく使われますが、リストラは必ずしも解雇を伴うものではありません。
一方、人員削減は文字通り人員を減らすための手段全般を言います。
- リストラ
事業再編や経営効率化のための施策全般
配置転換、部門統合などを含む - 人員削減
人を減らすための具体的な手段
退職勧奨、希望退職、整理解雇など
主な人員削減の例
- 新卒採用、中途採用の停止
- 早期定年退職制度の導入
- 希望退職、退職勧奨の実施
- 整理解雇
このなかでも整理解雇は、企業の経営悪化や事業再構築のために労働者を解雇することを意味します。
整理解雇には明確な基準があり、たとえば経営の必要性、解雇回避努力の実施、合理的な選定基準の適用、労使間の十分な協議が求められます。
なぜ人員削減は繰り返されるのか?背景にある3つの要因
主な原因:経済・技術・戦略の構造的な変化
人員削減の背景には、不況だけでなく、企業の構造的な変化や戦略の転換があります。
特に近年は「守り」ではないリストラが増加しています。
- 経済的要因
景気変動や市場の不確実性(リーマンショック、コロナ禍など)によるコスト削減 - 技術革新
AIやロボティクス導入によるルーチン業務の自動化により、人手が不要となる - 経営戦略の変更
不採算部門の閉鎖、事業再編。旧来の業務に従事していた人員が不要となる
増加する「攻めのリストラ」(黒字リストラ)
最近は、経営状況に余裕があるうちに行う「攻めのリストラ」、すなわち黒字リストラが増加しています。
企業として体力があるうちに、特定の職種や年齢層に対する希望退職を実施して、組織のスリム化を図るのです。
黒字経営ならば、割増退職金をだせる余力もあるので、将来的に不要になる社員に円満に退職してもらうことができます。
繰り返される人員削減が社内に与える深刻な影響
残った社員の不安とストレスの連鎖
人員削減が企業内で発表されると、社員の間に広がるのは「不安」と「ストレス」です。
一部の社員は自分が次に解雇されるかもしれないという恐れから、職場を軽視し始めることもあります。
結果として、希望退職の対象となる人だけでなく、対象年齢よりもしたの若年層の社員の退職も増えることがあります。
「そういうことする会社なんだ」って想いが社員の心に根付いてしまうんですよね
運よく退職せずに会社に残れたとしても、社員が減ったせいで一人当たりの業務量が増えてしまいます。
次の人員削減で対象にならないように頑張って仕事をしすぎて、心身ともに疲れて休職してしまう人もでてきます。
企業のブランドイメージへの影響
人員削減は企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性があります。
特に頻繁に人員削減を実施する企業は、経営が不安定であるとの印象を市場に与えます。
- 優秀な人材が集まりにくくなる
- 既存社員のモチベーションも下がる
- チームワークや企業文化が崩壊する可能性も
繰り返される人員削減は、長期的なビジネス成長にも深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。
筆者の実体験:リストラを2度経験して見えたこと
この記事を書いている筆者は、勤続14年で退職勧奨を受けました。
さらにその約10年前には、在籍していた部門が大手電機機器メーカーから人員削減の一環として切り離され、売却されるという経験もしています。
「捨てられた」というネガティブな感情からの脱却
「本社から捨てられた」「売却された」となると、社員の気持ちも落ち込みます。
せっかく頑張って〇〇社の社員になった!と思っていたのに、頑張っていた自分たちの部門が売却されるのですから、失恋したような気分です。
でも考え方を変えてみると、売却できる部門や子会社というのはある程度利益があったり、将来性がある事業内容ということです。
将来性がない会社をわざわざ買い取ってくれるような企業はいません。
買い取ってもらえない不採算事業はどうなるか?
事業の縮小で済めば良いところで、事業終了や最悪の場合は事業所丸ごと閉鎖で、異動先がない人は退職勧奨か整理解雇です。
筆者の在籍した部門は独立して、その後紆余曲折がありながらも東証プライムに上場しています。
本社の方もその後業績がV字回復したので、捨てられた側としては「ちょっと悔しいけど、まぁ良かったね」という気持ちです。悔しいけど。
大切なのは「次の可能性を見つけること」
会社都合退職に応じるのも、会社に残るのも、どちらも大変な選択です。
実際に経験した筆者の立場から言えるのは、「運が悪かった」「会社に捨てられた」と思うのではなく、「これを機に、次の可能性を見つけることが大切」ということです。
会社に依存せず、自身の市場価値を見直すきっかけにしましょう。
まとめ:会社に頼らないキャリアの構築へ
人員削減を繰り返す企業というのは結構あります。
体力のない企業の場合は残念ながらそのまま会社が傾く場合もありますが、大企業の場合は経営のスリム化によって業績が回復する場合も多いです。
いずれの場合も、社内の雰囲気悪化や業務量増加は避けられません。
- 社内の状況を冷静に分析する
- 自身の市場価値を客観的に見極める
- 会社が提示した次の機会(退職優遇や異動など)を、自身のキャリアプランに照らして検討する
会社に頼るだけでなく、常に「自分軸」でキャリアを考え続けることが、この時代を生き抜くサバイバル戦略です。
希望退職やリストラが実施されると、自分の将来・会社の将来について不安を抱いて当然です。
不安を感じるのは、具体的な数字やプランなどの根拠がないからです。
たとえば、「あなたの市場価値は年収800万円!」と診断されたり、「希望勤務地に求人が10件以上ある」など、数字に基づいた情報が増えるほど不安感は薄れます。
📌 リクナビNEXT:
まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。
自分のペースで探せ、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。
中高年向けの求人も意外と多め。
📌 doda:
求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。
ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。
📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:
本気でキャリアを見直したいなら。
中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。
どのサービスも無料で始められます。
「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。
\5分で簡単登録完了/